鹿児島県民の真実 ケンミンの秘密・極
ケンミン共生シリーズ「県民と火山灰」24/4/18
・鹿児島の象徴「桜島」は、年中噴火を繰り返す活火山。
・鹿児島県民にとって桜島の噴火は日常!?
・噴火より噴火後の火山灰が洗濯物にかかるのを気にしている!?
・降灰エリアは、噴火の規模+桜島上空の風向きにより変動する。
・ニュース番組に「降灰予想」がある。
・火山灰のおかげで土の水はけが良く、さつまいも作りに最適。
・そして、鹿児島県民は桜島が大好き!
3文字名字王国の秘密 鹿児島県民の真実 【鹿児島県】23/12/15
・鹿児島の名字には「上白石」「細山田」「上尾崎」など一般的な2文字の名字に1文字を加えた“3文字の名字”が多い!?
・上中下大小新古などの文字を加えることが多い。
・3文字名字の県民は、名前を呼ばれる時に最後の1文字をカットされがち!?
「上白石」「細山田」「上尾崎」など
・県西部の曽於市には「東別府」「西別府」「北別府」「今別府」など、名字に「別府」が入る県民がたくさんいる!?
・しかし、南別府はいない?が「上中別府」「岡別府(オカンビュウ)」などもある。
名字の多くは地名に由来
713年元明天皇が地名を漢字2文字で表すように命じたことから、日本人の名前は漢字2文字が多いと考えられている。
3文字になった原因は不明
明治8年に全国的に名字が義務づけられた。
何故か鹿児島では同じ名字を避けるべく地名に1文字足した名字が多く生まれた。
ケンミン聖地巡礼~本場の中の本場を探せ~「ごわす」23/3/2
・鹿児島弁を象徴するワード「ごわす」!?
・”ごわす”は、武家が好んで使っていたことば!?
・今ではほとんど使わない古い鹿児島弁
・令和の今でも日常で「ごわす」を使い続けている地域(聖地)があった。
・曽於市末吉町を「ごわす」の聖地に認定。
方言研究家・橋口滿さんの話
ごわすは、麓言葉として薩摩藩時代の武士が使っていた言葉
江戸時代に第十八代薩摩藩藩主・島津家久は、「人をもって城となす」という考えを打ち出し、これを「外城制度」という。
県内(旧薩摩藩)102か所に外城を設け、そこに武士集団を住まわせて統治させた。
その武家屋敷群=麓とといい、その麓の中で武士が麓言葉として用いた代表的なのが「ごわす」
鶴丸があった鹿児島市は、一番麓言葉が多用されていたが世事の中心から新しい言葉がどんどん生まれて、方言を使う機会が減っていった。
末吉町(末吉城)には、大きな麓があり多くの武士が移住してきて、日常的に「~ごわす」「~ごわした」と今なおよく使われている。
「鹿児島県枕崎市では、歓迎会で新任の先生が鰹の背皮を被る!?」22/4/14
・枕崎市は、全国有数の鰹の産地で鰹節の生産量日本一の地としても有名
・鰹の背皮被りは、枕崎市の春の風物詩となっている。
・背皮被りは、鰹節を作る際に余る背皮を乾燥させたものを被る。
・元々は、新人鰹節職人が自己紹介をする際に行っていた風習で、約30年前にPTAの方が新任先生の歓迎会に取り入れたという。
・新任先生の歓迎会では、鰹の背皮を被りながら、枕崎市のおもてなし料理「鰹のビンタ料理」を手づかみで食べる!?
・「鰹のビンタ料理」とはカツオの兜焼きで昔からのおもてなし料理で、ほぼ手で食べる。

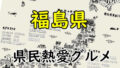
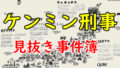
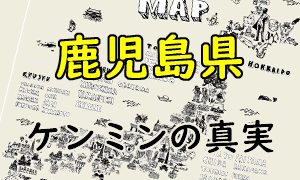
コメント